|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�T���E��V�V��
�@�@�@�@�@�@��2002�N�V��28���i���j��26����
���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c
�@�F���� �@���͂悤�������܂��B
�@���ɂ�B
�@������B
�@��V�V���ł��B
�@�p�\�R���̂k�`�m�̐ݒ肪���܂�������
�@������ƃC���C�����Ȃ���̐V���ł��B
�@�z���g�ɂ����I���Ċ����ł��B
�@����ł���ˁB
�@���������̂��āI
�@�C�����߂��Ȃ���s���܂��傤�B
�@���������[��������͂��܂肻���ȓ��C�s���炨���肵�܂��B
�@�F����̏��͂������ł����B
�@�܂��Ɂu�������������\���グ�܂��v�Ƃ��������ł��B
�@���āA�X�^�f�B�[�c�A�[�Q���҂��قڊm��ƂȂ�܂����B
�@22���̎Q���ł��I
�@��s�@�̃`�P�b�g�̎�z�A�p�X�|�[�g�̂��ƂȂǂ���
�@�����ȓ_�Ȃǂ���̂ł����A�Ƃɂ����ڕW��20���̒����܂����B
�@�z���g�Ɋ��ӂł��I
�@�ȉ���20���̌��C��ł̎Q���҃A���P�[�g�̏ł��B
�@�u�q���ƐG�ꍇ���c�A�[�͂������邯��ǁA
�@�w���ƍs������̂͂��̃c�A�[�����������B
�@���N��̐l�Ƃ̕����b���₷���������A
�@���݂��̍l�����̈Ⴂ�Ȃǂ����킩��C�����邩��B�v
�@�u�}���O���[�u�ɂ��ċ���������A�����}���O���[�u��
�@�����ɂ��ĕ��⓪�ōl���Ă��邾�������A
�@���H��̌����K�v���Ɗ����Ă������ɁA���܂��܁A
�@�V���ŋL�������ĎQ�����Ă݂����Ǝv�����B�v
�@���������ꕔ�Ȃ̂ł����A�ƂĂ������Q���ӎ��ŗՂ�ł���Ă���悤�ł��B
�@�܂��A���̓��{�̊w���ƈꏏ�Ɋ������Ă����x�g�i�����n�̊w���I�l��
�@���܂�܂����B
�@27���ɐΊۂ���ƃx�g�i���E�z�[�`�~���E�z���o����w Hung�w������k�B
�@���s���Ă��������g�����搶�����킹��17���̎Q���ł��B
�@�Q�����Ă��������x�g�i���w���Ɂu�������{�l�Ɍ��������z�[�`�~���v�Ƃ���
�@��ō앶�������Ă��炢�܂����B
�@�Ίۂ��킭
�@���{��͂܂��܂��ł����A���ӂ�������
�@���{���Q���҂��ē��������Ƃ����v�����`����Ă�����e�������ł��B
�@�܂��A�z���o����w�̊؍���w�Ȃ̐搶�A���k����
�@�����B�ɂ��Q�������ė~�����Ƃ̗v�]���o�Ă��邻���ł��B
�@�������A�؍��Łu��V�̉�v���K�v�ɂȂ肻���ł��B
�@�u���E���N�𗬂̐X�v�̎������ĊO������������܂���ˁB
���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c
�@����ł́A���T���Ίۂ���̌��n����̃R�������͂��Ă��܂��B
�@ �@dragon �R������27�e�u�����ł̏����v
�@�ŋ߁A�H��ŏ������Ă���l����������������i�x�@�j�Ɏ��グ����Ⴊ�A
�@�����x���^���s��ߕӂŕp�����Ă��܂��B
�@�����s���H��J�t�F�̕Ћ�����ă^�o�R���Ă���Loan������A
�@�ԗւ̂����ړ����V���E�P�[�X��2�T�����Ėv������܂����B
�@�������уW���[�X���Ă���Dung������o�̍i��@��v���ł��B
�@���̋@�B�ɂ��ԗւ�����܂��B�ԗւ�����̂ɂ͖���̂ł��B
�@�v���Ƃ����Ă��A���グ�Ĕp������Ƃ������Ƃł͂���܂���B
�@����10���h�����x������2�`3����ɕԊ҂���܂��B
�@�߂��Ă���Ƃ܂��A��l�́A���R�ƒʏ�ʂ菤�����͂��߂܂����B
�@���̂��߂̖v���������̂��S���킩��܂���B
�@�ᔽ���Ă����͂���Loan������̓X�ŁA�����𒅂��������^�o�R���B
�@�����NJ��O�Ȃ̂ł��傤�B����ȕ��i�͒��ю��Ȃ̂ł��B
�@�u������A���������~������B�^�����������ˁv��
�@Loan�������芪�����Ԃ́A�ڂ��ڂ��ƈԂ߂܂��B
�@�������{���ɈԂ߂Ă���悤�ł͂���܂���B
�@�����A���l�̕s�K���y����ł��镵�͋C������܂��B
�u�ŋ���[�߂Ă��Ȃ�����A���܂ɂ͐ŋ��������߂�����v��
�@�{�l�����Ȃ��Ȃ�ƁA���ɂ����b�������ăj���b�Ə��܂��B
�@�����̑�����Ƀ��[��������܂��B
�@���H�ɖʂ����Ƃ̎����傪�A�݂��̂ŕ��������邱�ƂɂȂ��Ă��܂��B
�@���̊�����m�Ȑ��l�K���ł͂Ȃ��悤�ł�����A
�@�����́A���H�ɖʂ����Ƃ̎v�f�őS���Ⴂ�܂��B
�@�ܑ��Ɏg���^�C�������܂��܁B�ܘ_���̃R���N���[�g�ܑ�������܂��B
�@���z���܂��܂��ł��B
�@�ł��邾�������̐l�ɏ����̋@���^����Ƃ����Ӗ�������̂ł��傤�A
�@�Ԍ���3�`5m���炢�ł��B
�@�ł���������������3�`5m���Ƃɒi���������܂��B
�@��Q�̂���l�Ȃnj����Ēʂ����̂ł͂���܂���B
�@�������o�C�N�⏤�i���u����A�ʂ��낤�ɂ��ʂ�Ȃ������������̂ł��B
�@�������������Ƃ��āA�Ƃ���1.5m�͐����҂̎g�p�����F�߂��Ă��܂��B
�@�����ɘH�㏤�����ł��鍪�������܂�܂��B
�@�^�o�R�����Loan����̓J�t�F�̎�����Hong�Z�B�ɉ������̒��ؗ�����
�@�����炭1�u�ɂ������Ȃ��ʐς��g���Ă���̂ł��B
�@Hong�Z�B�ɂ��Ă��A�����̌����ł���1.5m�͈̔͂�
�@�������Ă���킯�ł͂���܂���B
�@����3�{���炢�̕����Ј�t�ɁA�̃e�[�u������ׂĂ��܂��B
�@������u���������邼�I�I�v�Ə����܂����B
�@���܂ō����Ă����J�t�F�̋q���S�������̂ŁA�̃e�[�u���������݁A
�@�����Ă����֎q���d�ˁA1.5m�̈��S�n�тւƉ^�т܂��B
�@Loan������̎ԗ֕t���V���E�P�[�X���A�K���K���Ƃ������܂����������āA
�@���S�n�тɓ������݂܂��B
�@���̑O�𐔐l�̌������悹���W�[�v���ʂ�߂��Ă����܂����B
�@�V���E�P�[�X���e�[�u�������̈ʒu�ɖ߂�܂����B
�@�ԗւ͈ړ����}�����߂ɐ�ɕK�v�Ȃ̂ł��B
���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c���c
�@�����܂��������ł���ˁB
�@�������A���̕����͓��H�ɗאڂ���Ƃ����Ƃ������x
�@���{�l�ɂ͂Ȃ��Ȃ��������������ł���ˁB
�@���{�ƃx�g�i���A�ǂ������u�Љ��`�̍��v�Ȃ̂�
�@�킩��Ȃ��Ȃ�C�����܂��B
�@���āA��T�́u���Q�v�̃R�����ɂ��ւ�����������܂����B
�@�u�h���S���R�����w��2�x�̏d����Q���������l�̕`�ʁA
�@���L�V�R�ł��悭�������i������܂����B
�@����◼���̂Ȃ��l���X�p�ɂ��āA���L�V�R�ł͕��ł͂Ȃ��A
�@�~�T���K��K���₻�̑��̓y�Y�����Ă�����A
�@���邢�͒P�ɋʂ������Ă����肵�܂����B
�@��ɂȂ��āA���郁�L�V�R�����Ƃ̒����ǂ�ŋ���ł���܂����B
�@�ނ�̑̂̈ꕔ������ꂽ�����́A�ނ�̕n�����琶�܂ꂽ�A
�@����Ђǂ��K���ɂ���Ƃ����̂ł��B
�@�n�����ƒ�ɐ��܂ꂽ���ǂ��̂����̈ꕔ���A
�@���̎��̐e�ɂ���Ęr�⑫��ؒf�����̂������ł��B
�@�������ďd����Q�����������ǂ��́A�����A�ό��n�̊X�p�Ɂu�u����v�A
�@�[���ɂȂ�Ɣނ炪���̑̂̓����ɂ���Ă������������ƂƂ��ɂ��̉Ƒ���
�@�u����v�����Ƃ����}�������藧���Ă���Ƃ����̂ł��B
�@���L�V�R�̊X�p�ŁA�u���߁v�������镗�i�̗����ɂ́A
�@����Ȕ߂����A���������ȍ����ƁA����������Ȃ��n��������̂������ł��B
�@�x�g�i���ł́A�푈�≻�w��i�̎g�p�ȂǁA
�@�n���Ƃ͈قȂ錴��������̂�������܂��A
�@�ǂ̂悤�Ȏ���B����Ă���̂ł��傤���B�v
�@�u������ϋ����[���ǂ݂܂����B
�@�^�C�ł����l�ɁA�q�ǂ�����Q�҂̕�����ɂ悭�o��܂��B
�@���܂Ŕ��������Ƃ͂���܂���ł������A����͔������Ǝv���܂��B
�@�܂��A�^�C�ł���Q�҂̌�H���R���܂����B
�@�z�e���̋߂��̕������͂��̗l�Ȍ�H�ɐ�̂���Ă��܂��B
�@�q�ǂ��������Ă����āA�葫���ꂽ�肵�Č�H�ɂ����Ƃ����b��
�@��������������܂��B
�@�����Ɣߌ��̑啔���͕n�����琶�ݏo����Ă���Ǝv���܂��B
�@���ꂪ�q�ǂ������ɂ������Ă��邱�̌����A�������ɂ͉����o����̂��A
�@�ÑR����C�����ɂ������܂��B�v
�@����ɂ��ĐΊۂ�����ԐM���͂��Ă��܂��B
�@�u�x�g�i���̏�Q�҂ɂ������悤�Șb��������܂��B
�@�������A���̐e���A�܂��c���䂪�q��������Ƃ����b��
�@���������Ƃ�����܂���B
�@3�N���O�ɂȂ�܂����A��H�w�Z���E�����ꂽ�Ƃ����L����
�@�傫�����グ���܂����B
�@�r�⑫�𗎂Ƃ��菕���A�₯�Δ��ŕЖڂ��Ԃ�
�@��������ĕ���W�c������Ă����Ƃ����̂ł��B
�@�M�����Ȃ������ł����A�E�����ꂽ���Ƃ͎����ł��B
�@����A�H��̃J�t�F�ŃR�[�q�[������ł��܂����B
�@�ʁ[�Ɗ�O�ɐl�e�������܂����A���r�̂Ȃ������ł��B
�@�����𐿂��Ă���̂ł��B�ꂵ�݂��̑S�̂���ɂ��ݏo�āA
�@�ꌩ50�Α�Ɍ����܂����A���̐��A�̂����炵�Ă����炭30�Α�㔼�A
�@�����Ƃ�40�Α�O���̏����ł��B
�@ �u�ǂ����Ęr�������́H�ƕ����܂����v
�@ �u�����ł��v�Ɠ����܂����A�ڂ͉R�������Ă��܂���ł����B
�@�������A�|�P�b�g�ɓ���Ă����悤�Ƃ����Ƃ�
�@�ׂɍ����Ă����j���͂��̂Ă�悤�Ɍ����܂����A
�@�u���K�v�͂Ȃ��A�����́A�����Řr�𗎂Ƃ����I�I�v
�@�ǂ��炪�^�����킩��܂���B
�@�������A�s��Ȑ������ł���ˁA���̏������j���E�E�E
�@�r�𗎂Ƃ��Ă܂ł��i�j�̌������Ƃ��^�����Ƃ��āj�A
�@����̕����܂����ƍl���鐶�����B
�@�r�̂Ȃ��{�l��O�ɂ��āA
�@���R�Ɓu���ˁI�I�i���Ȃ���Ύ���������܂���j�v�ƌ������j�B
�@�ޏ��́A�G���������悤�ɐÂ��ɗ����Ă��܂����B
�@�G���ɍR�����Ƃ̖��Ӗ��������x�����킢�A�܂������
�@���܂����̂��̂悤�ɐÂ��ł����B
�@���͏������߂̂������|�P�b�g�ɓ���Ă��܂����B
�u���肪�Ƃ��v�A�Â��ɂ��������Ĕޏ��͋���܂����B
�@���ꂪ�A�ŕn�w�̌����ł��B
�@�ޏ��́A����Ƃ��l�O�ɑ̂����炵�A�Â��ɂ��������邱�Ƃ�
�@�����̐����Â��邱�Ƃł��傤�B�v
�@
�@�߂��������������ł���ˁB
�@���͍��A���É��w�ɋ߂Ă��܂��B
�@�w�̎��ӂ�H��ɑ����̃z�[�����X�̕����������܂��B
�@�z�[�����X�����͑傫�ȎЉ���ɂȂ��Ă��܂���
�@�ŋ߁A����̐l���Č������Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�@�z�[�����X�ł͂��邯�ǁA����ł͂Ȃ��B
�@���E�̊e�n�ɂ͕�������邽�߂Ɏ����̑̂̈ꕔ��
�@�q�����炾�̈ꕔ���������Ƃ܂ł��߂炦�Ȃ��l����������B
�@����肾���ł͂Ȃ�
�@�����Ƃ��낢��Ȍ��������邱�Ƃ�
�@�������͒m���Ă����K�v��������Ċ����܂����B �@
�@���̂��߂ɂ��撣���Ă����܂��傤�B
�@������ƃZ���`�ȃG���f�B���O�ɂȂ��Ă��܂��܂�����
�@���T�͂���Ȏv�������߂�
�@�ł͂܂����T�܂ŁA�����C�ŁI
�@(�ҏW�E�X�c�B��@�����^�c�j
���~���~���~���~���~���~���~���~���~���~���~���~���~���~���~���~
���u�T���E��V�V���v �@�@
�������́@nan-you@k7.dion.ne.jp�܂ŁB
==================================================
�� �z�M��~�̂��\�����݂ɂ��Ă���L�܂ł��A�����������B
==================================================
��V�̉� http://www.namdu.jp
================================================== �@�@ �@�@ �@
|
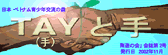 �@�@
�@�@