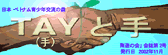|
週刊・南遊新聞
★2002年6月30日(日)第22号★
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
皆さま おはようございます。
こんちにわ。
こんばんわ。
南遊新聞です。
皆さん、お元気ですか。
モリタツのいるここ愛知県東海市は今、雨です。
小雨という感じです。
皆さんのところはいかがですか。
今日で6月も終わり。 一年の半分が終わってしまったこととなります。
早かったような。
そして盛り上がったサッカーワールドカップも今日の決勝で
幕を閉じます。
さあ、どっちが勝つんでしょうか。ドイツか。ブラジルか。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
昨日はこの夏のスタディーツアーの説明会を開催。
3名の方が参加してくれました。
ありがとうございます。
これからが楽しみです。
では、石丸さんからコラムをお届けします。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
drgon コラム 第23稿「地下足袋」
ハーさんはカンザー森林管理組合の4人いる若手研究員の中心人物です。
地下足袋を愛用しています。
彼の地下足袋はもともと私のものでした。
昨年はじめて森の奥地に案内していただいたときに使っていました。
膝下まで覆える少し長めで、田植え用のものです。
現地の状況を聞いたワークマンのご主人に進められ、求めたものです。
ただ、失敗したのは、使うにつれサイズが変化することに
気づかなかったことです。
コハゼで止める部分は、かなりの自由度があるのですが、
足先の方は、そういかないのです。
はじめにきっちりしたものを求めますと、厚めの木綿の生地は収縮します。
特に濡れているときには、収縮して足先を締め付けます。
その結果、足全体がはれ上がったりします。
私の場合も、実際に使ってみてそれがわかりました。
ワンサイズ大き目のものがそのうちにピッタリと馴染んできます。
ハーさんの地下足袋は、私が前に使っていたものを差し上げたものです。
収縮して、私の足が入らなくなってしまいました。
彼らも作業靴を支給されています。
厚底でつま先には金属板が入っています。登山靴のようなもので、頑丈です。
しかし重いのです。
滑り易い気根の上に乗ったりしますと、硬い靴底がさらに滑り易さを強めます。
逆にずぶずぶの泥沼に入りますと、この重い靴では動きが大変です。
その点、地下足袋は軽い上に、足全体との一体感があり、
滑り易い気根の上でも、薄くて柔らかい底で、気根を掴む感じになります。
泥沼でも足そのものの動きに自然に馴染んできます。
その上、厚手の木綿はぬれると強くなるんですね。
ジャングルの中の少々の切り株や刺のある木でも跳ね除けます。
まさに優れものです。
ハーさんはとても気に入って、以降、森の奥地に入る時には、
必ずこの地下足袋です。
ゴム長はたくさん見かけます。
しかし、地下足袋は見かけたことがありません。
ベトナムで障害者が多い原因の一つは、裸足生活です。
田んぼでも殆ど裸足。
最近カンザーで、一部森を切り開きました。
残った切り株を掘り起こしたり、落ちた枝を拾いに入る女性の殆どは裸足です。
とがった切り株がそこここにあります。
泥の中にも、危険なものがいっぱいあります。
傷ついて、破傷風に冒される人が結構いるようです。
冒されるとすぐ切断です。
きっと、ベトナムの皆さん、地下足袋に馴染むと思います。
生ゴムはベトナムの特産品、木綿も十分取れます。
縫製技術も最近は向上して、縫製品の輸出は伸びています。
ベトナムの産品としてぴったりではないかと思います。
材料も労働力も安いですから、きっと安くできると思います。
輸出もしやすいと思います。
単に人件費が安いから進出するというのではなく、
付加価値を進出国に残し、かつ消費も促す。
それがベトナムの皆さんの安全や健康に貢献できるとしたら
こんな素晴らしい進出のあり方はないように思います。
大王足袋さん、万年足袋さん如何でしょうか?
ひょっとしたらすでに進出なさっていらっしゃるかもわかりませんが・・
注)大王足袋、万年足袋は、私が購入した地下足袋のブランド名です。
正式の会社のお名前は存じ上げません。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
「エスキモーに氷を売る」なんて本が話題になっていますが
ベトナム人に地下足袋を売るのは、理に合っているかもしれませんね。
スタディーツアーに参加の皆さんも地下足袋は必須ですね。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
この南遊新聞の読者で日本に留学されていて今はベトナムに戻られた
ハイさんからお便りをいただきました。
ハイさんの故郷・古都フエの話題です。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
私の故郷:「古都フエ」
人口の30万人がいる古都フエは
ベトナム中部の政治・文化・旅行などの分野の中心となっています。
1993年12月にユネスコーに世界文化遺産として認められました。
戦争にひどく破壊されてもフエ王宮はベトナムの唯一建築が残ります。
フエ料理、文化、フエ人の性格、フエ訛りはどのところにも似ていません。
ベトナムで一番綺麗なフーン川(香川)はフエ市内をゆったりと流れたり
北の新市街と南の旧市街に分けます。
旧市街にはよく調和して阮王朝式(グエン王朝)の建物と
近代な建物が立ち並んでいて、
旧市街から西の6kmのところにあるのティエン・ムー寺はフエのシンボルです。
他の都市と比べるとフエは静かで緑と寺院、歴代皇帝の陵が多い町です。
どこを歩いても昔の遺跡が見えて、懐かしくて気持ちがいいです。
我が父の出身地はフエから10Kmの東南に地位するところです。
小さい時に石碑やさんとしての父に従って何回フエ市に来たことがあります。
その時はフランスの植民地時代です。
女学生ではなく女性の売り手さんもいつもアオザイを着たり、
夜にフエ人々は勇んでハットボイ(ベトナムの歌舞伎)を見に行ったり、
船頭さんは船を漕ぎながなよく悲しい民謡の歌を歌ったそうです。
今はそんなことははやっていません。
伝統的なことを回復するために時間がかかります。
高校女生は月曜日と土曜日に白いアオザイを着なければならないし、
おばあさんとおじいさんが大好きなハットボイクラブも成立されたり、
宮廷音楽はよく綺麗なフーン川(香川)の船の中で演奏されたりしています。
5年前に日本政府の援助でフエ芸術大学は雅楽クラスを開きました。
最近、民族音楽器を学ぶ若者がだんだ多くなります。
それは嬉しいしるしではないでしょうか。
「昔と比べるとまだまだですが、
地方の指導者は正しく伝統文化の継承・発達する政策を立てると
まもなく前のように復活できますよ」と父が言いました。
1986年から「ドイモイ」とよばれる改革政策によって、
市場経済が導入されると経済は飛躍的に発展しました。
1991年から建築ラッシュが大都市にひろがり、
住宅・ホテル・レストランなどの建築も進められています。
その傾向に対してフエに文化遺産保存修復の動きが大きく広がっています。
修復は1982年以来、文化省の下に設立された
「フエ遺跡保存センター」によって進められます。
「私はベトナムも、また世界的にも貴重なフエの歴史的遺産保存と言う仕事に
携われて嬉しく思っています。
私達スタッフは私同様この保存修復事業に愛国心を持って当たっています。」
フエ遺跡保存センターのディレックターのタイ・コン・グエンはそう発表しました。
そんな人たちのおかげで、失ったフエ姿はだんだん再現されています。
そういう理由で外国観光者ではなくベトナム人もよく
フエに引き付けられえています。皆さんはどう思いますか。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
ハイさん、ありがとうございました。
日本語でお書きいただき、感謝です。
古都フエ。
日本の京都のようなところと聞いたことがあります。
新しさと歴史的な建物が上手に共存できる街づくりが
進められるといいですよね。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡
それでは、皆さん。
明日から7月。
今年の1年の後半も頑張っていきましょう。
ではまた、来週!
(編集・森田達也 モリタツ)
☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ☆ミ
○「週刊・南遊新聞」
おたよりは nan-you@k7.dion.ne.jpまで。
==================================================
▽ 配信停止のお申し込みについても上記までご連絡ください。 =================================================
南遊の会 http://www.namdu.jp
==================================================
|